アロマって何?どんなものなの?そんな疑問にお答えします!
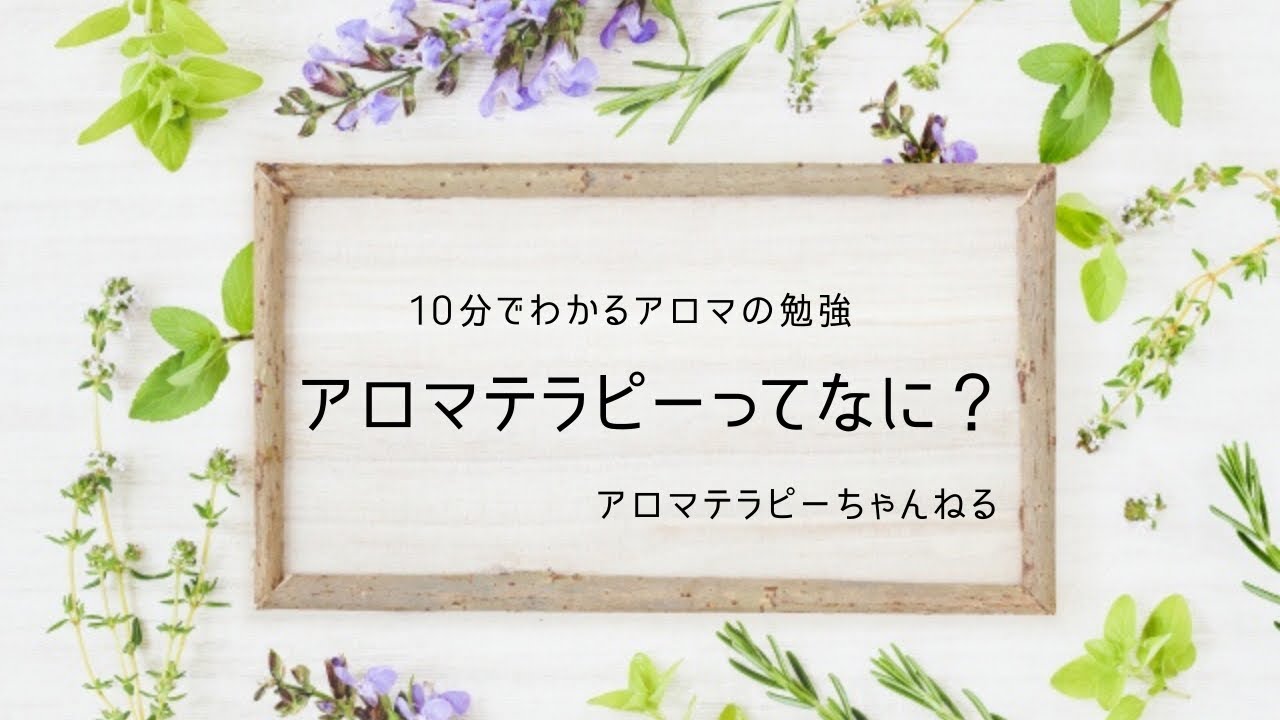
みなさんは、アロマテラピーについてどんなイメージを
僕がアロマの勉強を始めた頃、友達に聞いてみたことがあります。
アロマってどんなイメージがある?

なんか、香りのやつ?
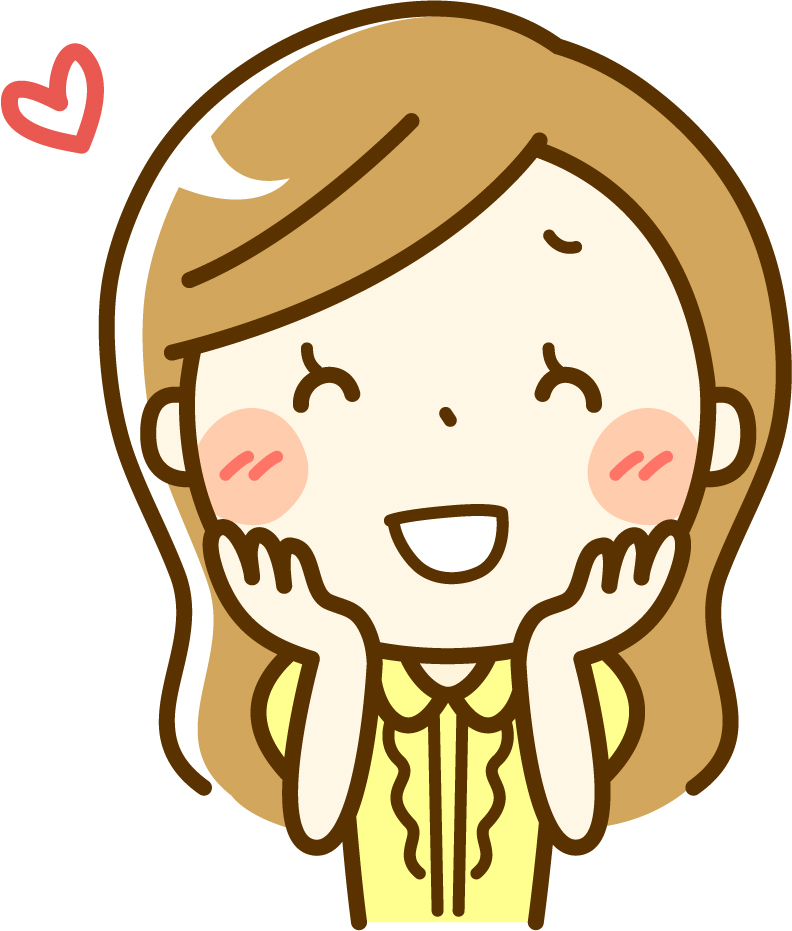
癒されるやつ?

クサイやつ
最後の人、何があったの!?
目次
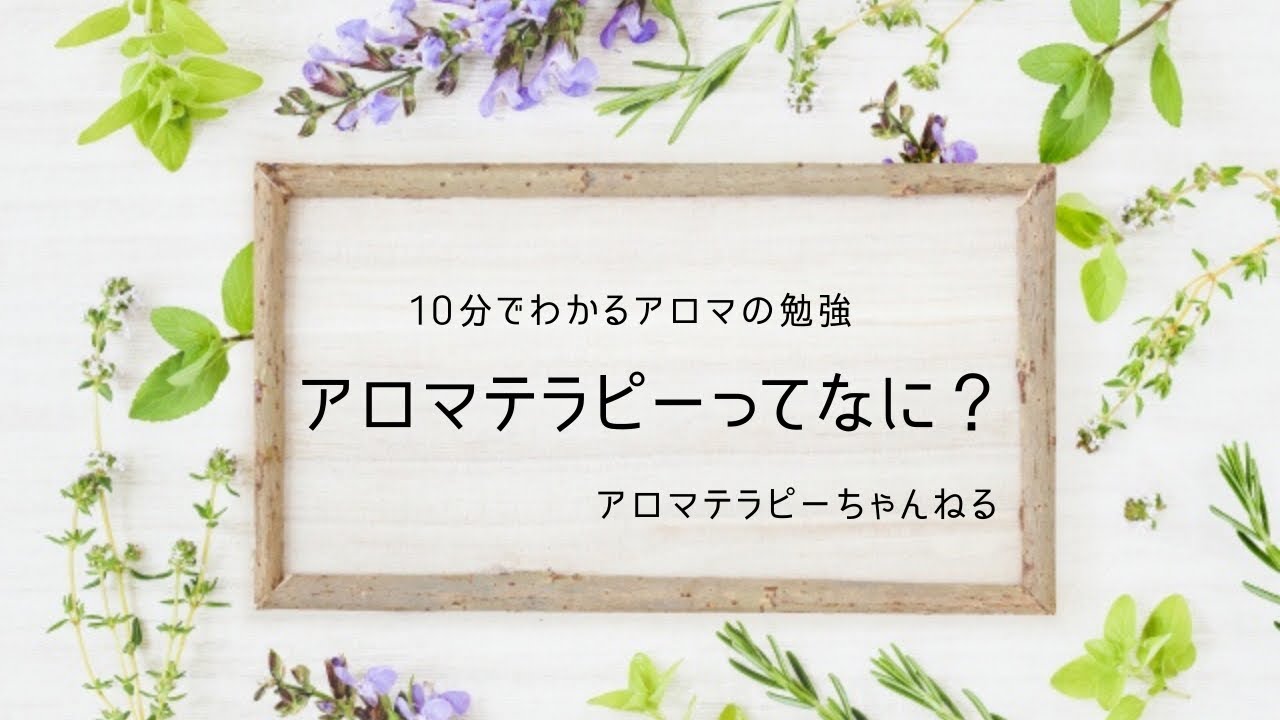
みなさんは、アロマテラピーについてどんなイメージを
僕がアロマの勉強を始めた頃、友達に聞いてみたことがあります。

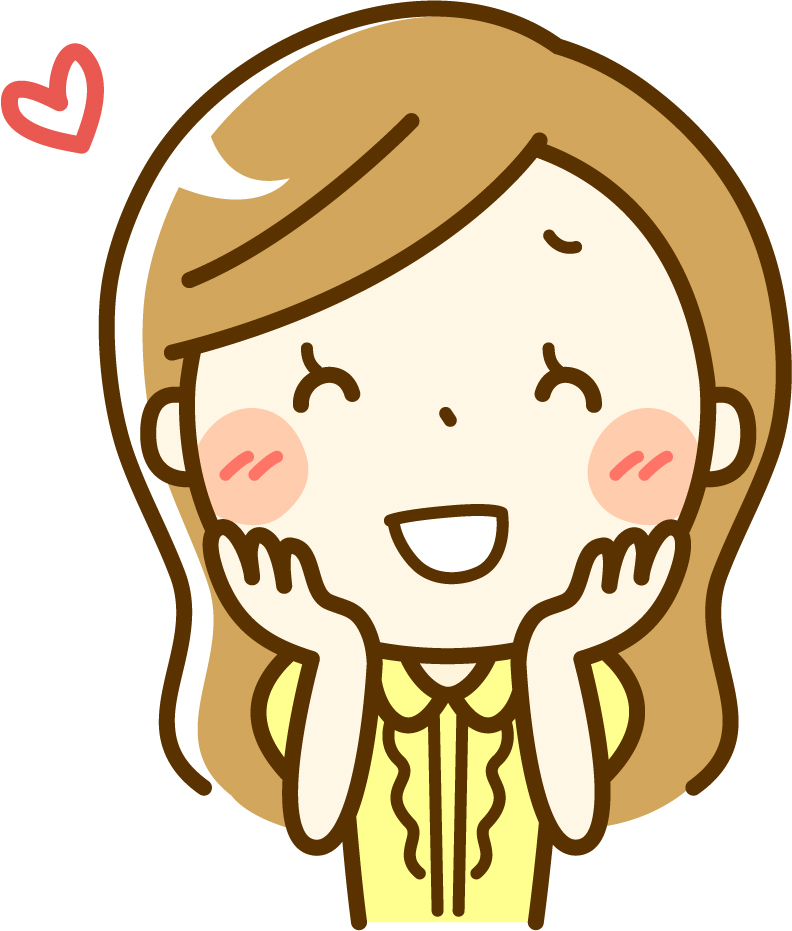

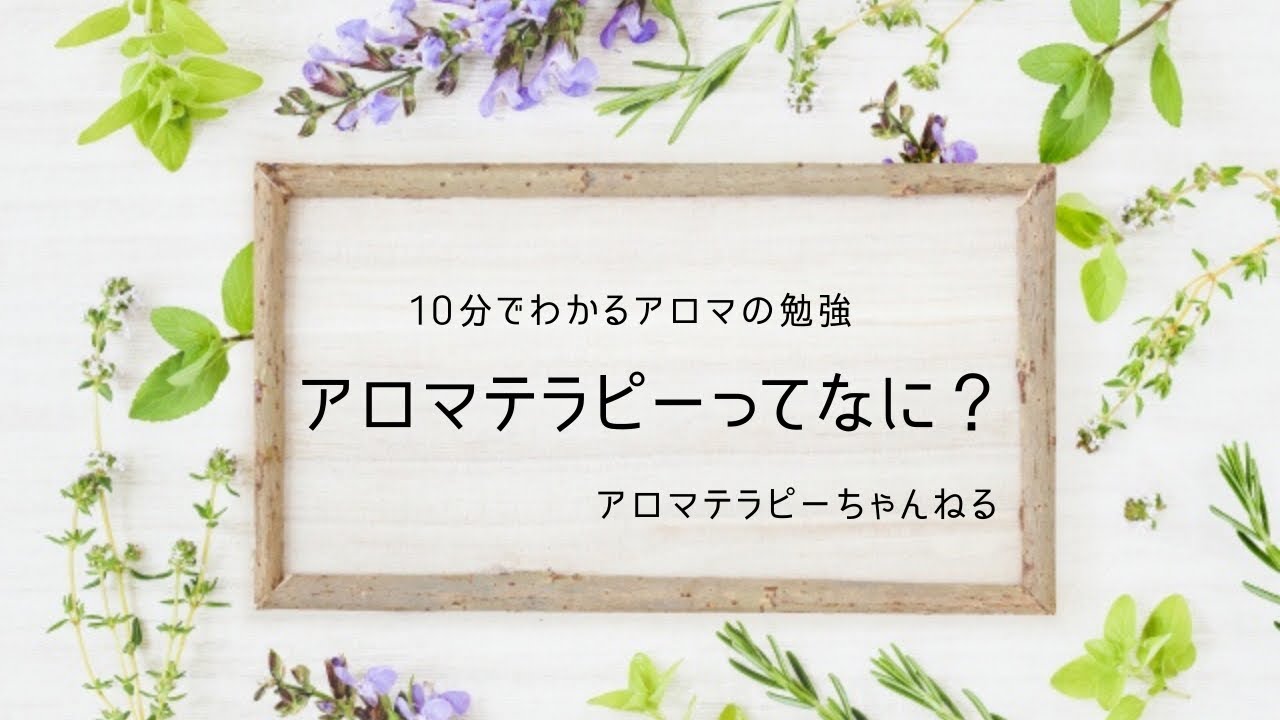
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!